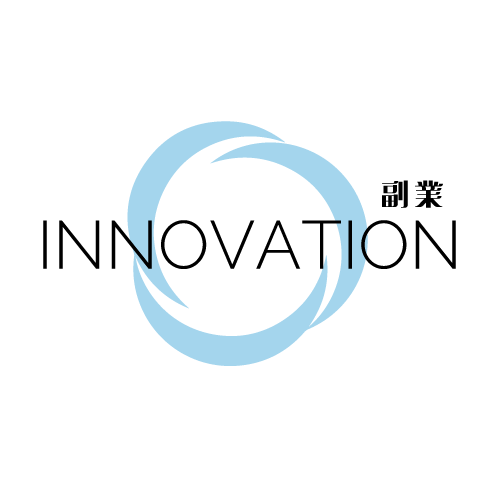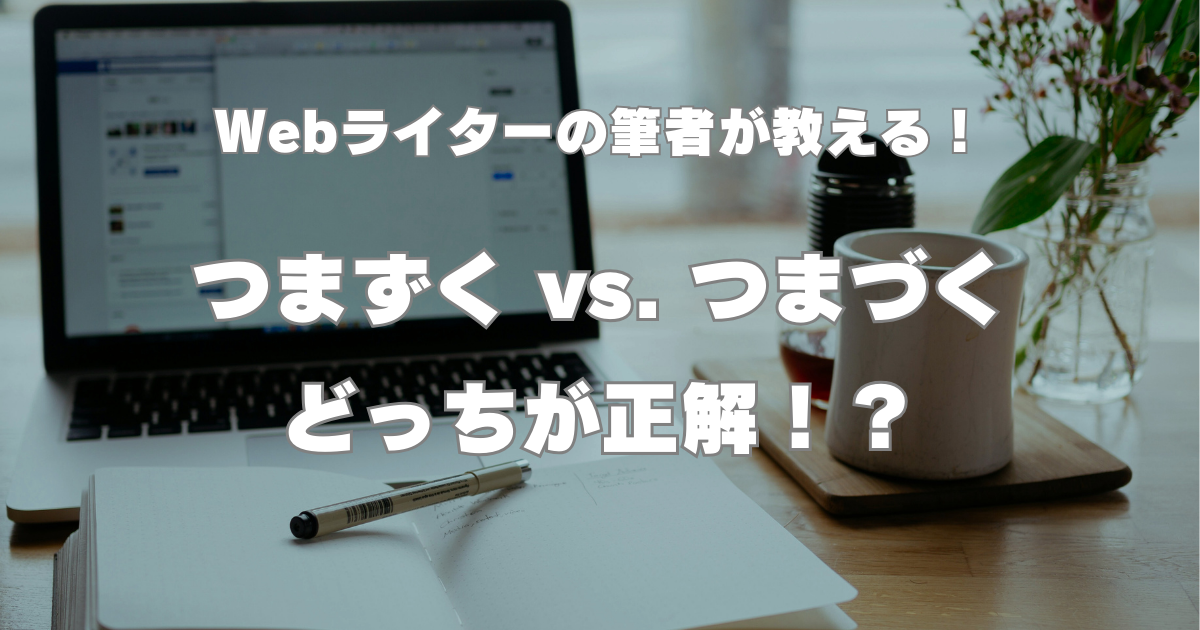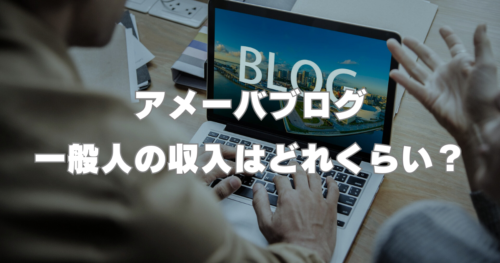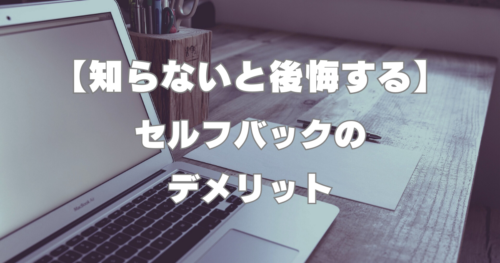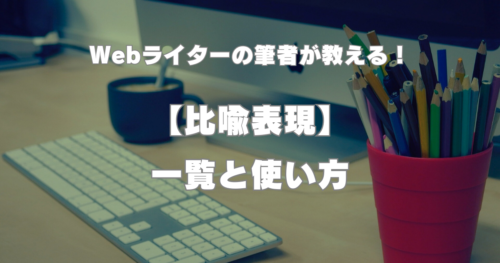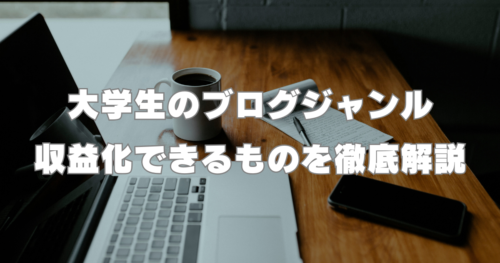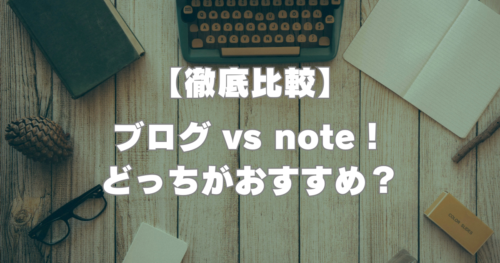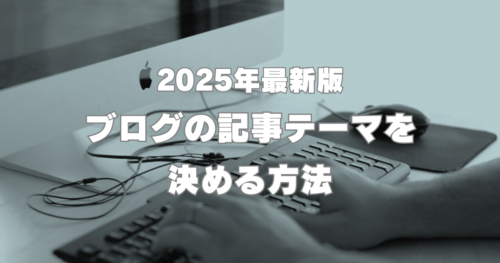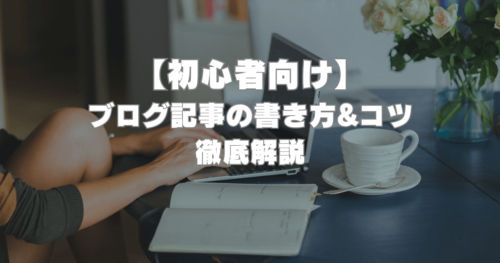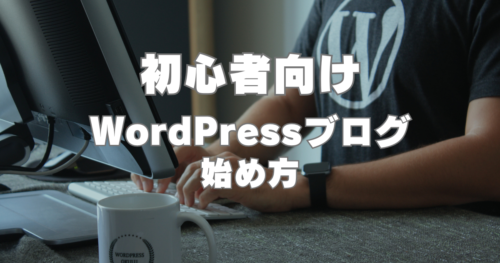「つまずく」と「つまづく」、どちらが正しいのか迷ったことはないだろうか。
ネットや書籍を見ても両方の表記が使われており、どれが正しいのか判断に困ることがある。
ライターやブロガーにとって、言葉の正確性は重要だ。
文章の信頼性を高めるためにも、正しい表記を理解し、適切に使い分けること が求められる。
この記事では、「つまずく」と「つまづく」の違いを明確にし、例文を交えながら正しい使い方を解説する。
さらに、副業ライターが知っておくべき表現のポイントについても触れていく。
✅ 「つまずく」と「つまづく」のどちらが正しいのか?
✅ 国語辞典・文化庁の見解をチェック!
✅ 使い分けの具体例と間違えやすい類語
✅ 副業ライターが知っておくべき表現のポイント
文章の正確性を高め、読者に伝わるライティングを目指そう。
「つまずく」と「つまづく」の違い
「つまずく」と「つまづく」は、同じ意味で使われることが多いが、厳密には異なる。
正しい表記を知ることで、文章の正確性を向上させることができる。
1. 「つまずく」と「つまづく」の意味
✅ つまずく(正しい表記)
- 意味: 足が何かに引っ掛かってよろけること
- 例文:
- 「石につまずいて転んだ」
- 「仕事でつまずくこともあるが、そこから学ぶことが大切だ」
✅ つまづく(誤用とされる表記)
- 意味: 「つまずく」の口語的な表現
- 例文:
- 「階段でつまづいた」 → 本来は「つまずいた」が正しい
 はると
はると話し言葉では「つまづく」も使われるが、正式な文章では「つまずく」を使うのが望ましい。
特に、ライティングの場面では、標準的な表記を選ぶことが重要になる。
どちらが正しい?国語辞典・文化庁の見解
「つまずく」と「つまづく」、どちらを使うのが正しいのか。
この疑問を解決するために、辞書や文化庁の見解を確認してみよう。
1. 国語辞典での記載
主要な国語辞典では、「つまずく」が正式な表記とされている。
✅ 広辞苑(第七版)
- 「つまずく」: 足を何かに引っ掛けてよろめく。また、失敗すること
- 「つまづく」: 掲載なし
✅ 新明解国語辞典(第八版)
- 「つまずく」: 足を何かに引っかけて、転びそうになる。また、比喩的に「失敗する」という意味でも使われる
- 「つまづく」: 掲載なし
2. 文化庁の見解
文化庁の「言葉に関する問答集」では、「つまずく」が標準的な表記であり、「つまづく」は誤用とされることが多いとされている。
✅ 文化庁の指摘
- 「つまずく」が正式な表記
- 「つまづく」は口語では使われるが、公的な文章には適さない
✅ ポイント
- 書籍・新聞・公的機関の文章では「つまずく」が使われる
- 「つまづく」は話し言葉では違和感なく使われるが、文章には適さない



副業ライターとしては、「つまずく」を使うのが正解。
文化庁や辞書の見解に基づいた正しい表記を使うことで、文章の信頼性を高めることができる。
例文で比較!使い分けの具体例
「つまずく」と「つまづく」、どちらを使うべきか迷ったときに、実際の文章でどのように使われるのか を確認してみよう。
1. 日常会話での使い方
✅ 正しい例
- 「駅の階段でつまずいて転びそうになった」
- 「暗がりで石につまずいてしまった」
❌ 誤用(会話では通じるが、公的にはNG)
- 「昨日、玄関の段差でつまづいたんだよね」
- 「歩いてたら小石につまづいた」



話し言葉では「つまづく」も使われることがあるが、文章では「つまずく」が正しい。
ライティングでは、「つまづく」を使わないように意識しよう。
2. 比喩表現としての使い方
✅ 正しい例
- 「人生には何度もつまずくことがあるけれど、それを乗り越えることが大切だ」
- 「プロジェクトの初期段階でつまずいてしまったが、チームの力で挽回できた」
❌ 誤用
- 「彼はキャリアで何度もつまづいたが、最後には成功した」
- 「新しいビジネスを始めたけど、最初でつまづいた」



比喩表現でも、「つまずく」を使うのが正しい。
「つまづく」は、公的な文章では違和感が出るため、避けたほうがよい。
3. ビジネス文章やフォーマルな文書
✅ 正しい例
- 「新規プロジェクトの初動でつまずいてしまったが、迅速に修正を行った」
- 「マーケティング戦略につまずき、売上が伸び悩んでいる」
❌ 誤用
- 「商品開発の途中でつまづき、納期が遅れてしまった」
- 「新しいシステムの導入でつまづいたため、改善策を検討中」



ビジネスシーンでは「つまずく」一択。
公的な文書や企業サイトの記事では「つまづく」を使わないように注意しよう。
比喩表現やビジネスシーンでも、「つまずく」が正しいとわかったね。
ライティングの精度を上げるために、しっかり意識して使い分けよう。
類語や間違えやすい表現
「つまずく」と似た意味の言葉は、他にもいくつか存在する。
言葉の意味を正しく理解し、適切な場面で使い分けることが重要だ。
1. つまずくの類語
✅ ① こける
- 意味: 転ぶ、倒れる
- 例文: 「足を引っかけてこけた」
💬 筆者のアドバイス
「こける」は完全に転ぶ場合、「つまずく」は転びそうになるが持ちこたえる場合に使う。
ニュアンスの違いを意識して使い分けよう。
✅ ② よろける
- 意味: バランスを崩してふらつく
- 例文: 「電車が急停車して、思わずよろけた」
✅ ③ しくじる
- 意味: 失敗する(比喩的な表現)
- 例文: 「プレゼンの冒頭でセリフを忘れ、完全にしくじった」



「つまずく」は「失敗する」という意味でも使えるが…、
ビジネスの場面では「しくじる」のほうがしっくりくることもある。
2. 間違えやすい表現
✅ ① 「転ぶ」と「つまずく」
- 「つまずく」: 転びそうになるが、持ちこたえることもある
- 「転ぶ」: 完全に地面に倒れること
✅ ② 「つまづく」と「つまずく」
- 「つまずく」: 正しい表記(国語辞典・文化庁の推奨)
- 「つまづく」: 口語的な表現(公的な文書ではNG)



「つまずく」は比喩的に「失敗する」とも使えるが、「転ぶ」はそういう使い方はできない。
この違いを意識して使い分けよう!
間違えやすい表現や類語をしっかり押さえておけば、より正確な文章を書けるようになる。
ブログや副業ライティングでも、この違いを意識して使いこなそう。
副業ライターが知っておくべきポイント
副業ライターとして記事を書く以上、言葉の正確性は欠かせない。
特に、よく使われる表現でも誤用が定着しているケースがあり、プロとしては正しい知識を身につけておくべきだ。
ここでは、ライターが意識すべきポイントを解説する。
1. 正しい表記を使う意識を持つ
✅ 「つまずく」が正しい
- 誤: 「仕事で大きくつまづいた」
- 正: 「仕事で大きくつまずいた」



文章の信頼性は細かい部分で決まる。
誤用を防ぐために、記事を書く前に辞書や文化庁の見解を確認する習慣をつけよう。
2. 読者にとって分かりやすい表現を選ぶ
✅ 比喩を多用しすぎない
- 「つまずく」は「失敗する」の意味で使えるが、読者が直感的に理解しやすい表現を選ぶことが大切だ。
✅ リズムを意識する
- 悪い例: 「彼の人生は、まるで大海の荒波のように、時には穏やかで、時には嵐のような困難が待ち受けていた」
- 良い例: 「彼の人生は、穏やかな波と嵐が交互に訪れる大海のようだった」



比喩は適度に使うのがポイント。
読者がストレスなく読める文章を意識しよう。
3. リサーチを怠らない
✅ 辞書・公式サイトで確認する
- 文化庁の「言葉に関する問答集」などを参考に、正しい表記を確認する
✅ 信頼できる情報源を使う
- SNSや個人ブログの情報だけを鵜呑みにせず、辞書・新聞・公的機関の情報 を元に記事を書く



「なんとなく」で使っている言葉ほど、実は誤用が多いもの。
リサーチを徹底することが、プロのライターとしての差を生む!
4. SEOを意識した表現を心がける
✅ 「つまずく 使い方」などの検索キーワードを意識
- 「つまずくとつまづくの違い」 など、検索意図に沿った表現を選ぶ
✅ 読者が検索しやすい言葉を使う
- 難しい表現より、読者が使いそうなシンプルな言葉を選ぶ



SEOを意識しながらも、不自然にならない文章を心がけることが大事。
「読者が知りたいことに正確に答える文章」を意識しよう!
副業ライターとして、正しい日本語を使いこなせるようになることは、文章の信頼性を高める大きな要素 だ。
細かい部分にも気を配り、読者に伝わる文章を目指そう。
まとめ・正しい日本語で文章力を高めよう
「つまずく」と「つまづく」は、日常でよく使われる表現だが、ライターとしては正しい言葉を選ぶことが求められる。
本記事では、「つまずく」が正しい表記である理由や、間違えやすい表現の使い分け について解説した。
1. この記事のポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正しい表記 | 「つまずく」が標準的な表現、「つまづく」は誤用 |
| 辞書・文化庁の見解 | 主要な国語辞典に「つまづく」は掲載されていない |
| 使い分けの具体例 | 「階段でつまずく」「人生につまずく」など、文脈に応じた使い方 |
| 類語との違い | 「つまずく」は転びそうになる、「転ぶ」は完全に倒れる |
| ライターが意識すべきこと | 正しい表現を使う、SEOを意識した文章を書く、リサーチを怠らない |
2. 正しい日本語を使うために意識すべきこと
✅ 言葉の正確性を意識する
- 「つまずく」か「つまづく」か迷ったら、辞書や文化庁の公式見解を確認する
- 公的な文章やビジネス文書では、誤用を避ける
✅ 読者にとって分かりやすい表現を選ぶ
- 難しい表現よりも、シンプルで直感的に理解できる言葉を使う
✅ SEOを意識しながらも、不自然にならない文章を心がける
- 読者が検索しそうなキーワードを取り入れつつ、自然な流れを意識する



言葉の使い方ひとつで、文章の信頼性は大きく変わる。
「この表現は本当に正しいのか?」と一度立ち止まって考えるクセをつけよう!
3. これからできる実践アクション
✅ 文章を書く前に、言葉の正しさをチェックする
✅ ライティングで迷ったら、文化庁や辞書の情報を確認する
✅ 誤用しやすい表現のリストを作成し、自分の文章と照らし合わせる
副業ライターとして、日本語の正しい使い方を理解し、読者に伝わる文章を書くことが大切 だ。
細かい部分にも気を配り、文章力を向上させていこう。